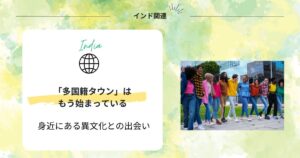島根の地に想いを寄せて──『砂の器』を読んで
石見銀山からもう一歩、島根つながりの読書
目次
島根県の石見銀山を訪れる機会がありました。
その際に読んだ小説が『しろがねの葉』。銀山をめぐる人々の暮らしや葛藤を描いた素晴らしい作品でしたが、「せっかくなら、もっと島根に関する物語を読んでみたい」と思い、検索でたどり着いたのが松本清張の『砂の器』でした。

砂の器 松本清張 著
舞台の一つ、島根県の亀嵩(かめだけ)には残念ながら今回の旅では立ち寄れませんでしたが、その地に思いを馳せながらページをめくる時間は、旅の延長線のようでもありました。
ただの推理小説じゃない『砂の器』の深さ
『砂の器』は殺人事件にまつわる推理小説と思っていましたが、読み進めるほどにそれだけじゃないと気づかされます。
殺された男性の身元を追っていくうちに浮かび上がってくるのは、「差別」と「過去」、そしてそれを隠し続ける主人公・和賀英良の苦悩。刑事・今西が「何かがおかしい」と直感を信じて捜査を続ける姿にも心を打たれました。
ラストまで緊張感がありつつ、じんわりと切ない読後感が残ります。
和賀英良という人物に感じたこと
成功した作曲家・和賀英良。その表向きの華やかさと、内側に隠された出自や家族のこと。
読みながら何度も「なぜ、彼はここまでして過去を隠したのか?」と考えました。
そこにあったのは、ハンセン病への差別という、現代の私たちからすれば信じがたい現実。
和賀が罪を犯したことは決して肯定できませんが、過去を知られたくなかった、という人間らしい思いが根底にあったのだと知ると、単なる「犯人」とは言い切れなくなってしまいます。
“砂の器”というタイトルに込められた意味
読み終わってから、ふと立ち止まったのがこのタイトルの意味でした。
「砂の器」とは、どんなに形を整えても、少しの衝撃で崩れてしまう——そんな儚く、もろい存在。
それは人間の幸せや立場、あるいは築き上げた人生そのものを表しているのかもしれません。
和賀の人生も、まさに“砂”の上に築かれていた。
物語では、器が完成して、人生を謳歌することができる、その直前に器はもろくも崩れ落ちました。
まさにこの状況自体が「砂の器」でした。
物語の中でそのことに気づいたとき、胸の奥が静かに締めつけられました。
最後に:行けなかった場所が、心に残る場所に
島根の亀嵩には行けなかったのですが、物語の中でしっかりとその地の風景を思い描くことができました。
旅では訪ねられなかった場所が、読書を通じて心に残る場所になる——そんな体験も含めて、この本との出会いは思いがけない贈り物でした。
『砂の器』は、推理小説の枠を超えて、「人間とは何か」「守るとは何か」を問いかけてくる、深く静かな作品でした。
またひとつ、島根という土地が、私にとって特別な意味を持つ場所になりました。