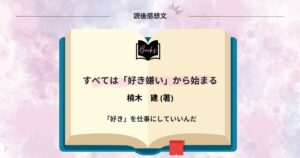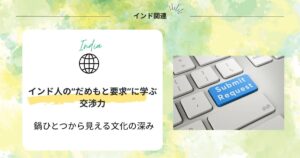インド人は風邪でも血液検査!? 日本人が驚くインドの“安心文化”
はじめに:風邪ぐらいで血液検査? と思ったら
目次
「風邪ぐらいで採血って…どうしちゃったのよ?!」とインド駐在初年度で感じたことです。
頼りにしているドライバーさんから、朝一番に「風邪気味なので、血液検査をしてから出社します。なので朝は代わりのドライバーです」 との連絡がありました。
インドでは、軽い風邪の裏にデング熱やマラリアが潜んでいることがあるため、まずは血液検査。
ちょっと大げさ?いえいえ、これが命を守るスタート地点なのです。
※インドでは道路事情が混沌としており、会社ではドライバーを用意してくれていました。かつ私はインドでは運転禁止でした(事故があった場合の対応困難となるため)。
道路事情の事例を一つ挙げます。
ドライバーさんは右折する際、直前に右側を気にしています。
何を気にしているのか? と思ったら、右折する瞬間にバイクが猛スピードで車の右側をすり抜けました…。幸い危うく衝突する直前に車が止まり、事故にはなりませんでした。
「私はこの国では運転できない・・」と思った瞬間でした。
では、話を「風邪と血液検査」に戻します・・・
最新デング熱事情—インドと世界の現状
世界規模では、2025年1〜7月だけで400万件以上のデング熱報告、3000人以上の死亡がWHOに報告されています(世界保健機関)。
記録的だった2024年には1,460万件以上の感染と、1万2000人以上の死亡も報告されています(世界保健機関+2WHO+2)。
インド国内では、2025年上半期だけで13,052件のデング熱と19人の死亡が報告され、特に南部のケララ州で多数を占めています(The New Indian Express)。さらに、2024年の全国累計は230,000件超と、2019年の約157,000件から大幅に増加しています(Gavi+2国立感染症研究所+2)。
都市部でも感染が拡大しており、たとえばムンバイでは2025年8月に1,159件、ノイダでは1週間で34件、ルクナウでも1日で10件と急増中です(The Times of India+8WHO+8sansad.in+8)。
風邪 vs デング熱:処方の違いが命を左右する
風邪とデング熱は、症状はそっくりでも、中身は全然違います。
風邪なら、解熱鎮痛薬や咳止め、抗ヒスタミン剤…と穏やかな処方。
しかし、デング熱に一般的な解熱・鎮痛・抗炎症のイブプロフェン(NSAIDs)を使ってしまうと、血小板減少で出血リスクが急上昇。最悪、“出血”で命を落とす原因にもなり得ます。
なので、インドではまず採血で「本当の原因」を見極めるのが鉄則です。
「とりあえず検査」の、マジなユーモア文化
日本で「念には念を入れよ」って言葉がありますが、インドではそれを超えて、「念には検査を入れよ」と言いたくなるほど。
ちょっとした不調でも「いや、血液検査が必要!(安心の儀式)」がセットになっているのが文化。
特定技能生との“血液検査お願い”珍道中
先日、インドから来た特定技能生が「胃が張る」「胸がかゆい」とのことで病院へ同行しました。
胃腸科ではレントゲン撮影・診断済みだったのですが、本人が「先生、血液検査お願いします!」。
医師は一瞬フリーズした後、「まぁ、ご希望なら…」と丁寧に対応してもらいました。
皮膚科でも、顕微鏡まで駆使して皮膚の状況を診察していただいた先生にまた「血液検査お願いします」。
今度も「かゆみの原因は分かったので、処方には影響ないけど…」と前置き付きでOKに。
彼は一言、「インドではいつも検査するから、日本でも必要です」。
なるほど、「採血されれば安心」という安心スイッチがしっかり備わっている…。
まとめ:「念には検査を」が生き残る知恵
これは単なる笑い話ではなく、実は合理的な文化。
「ちょっと過剰かな?」と思えるほどの予防が、命を守る大切な習慣になっているのです。
日本では「医師が不要と言えばOK」ですが、インドでは患者が「いや、ちゃんと検査して安心したい」と粘る姿勢が珍しくありません。
それはまさに「安心は結果が出てから」が基本の、安全第一文化です。
おわりに:笑いと学びの医療文化理解
インドの血液検査文化、笑えるけれど侮れません。
発熱や不調があるたびに検査を重ねる安心志向は、背景に「軽症が重大疾患かもしれない」という現実があります。
国際人材や家族が関わる時、日本人から見るとちょっと意外な行動も、「ああ、安心が欲しいんだな」と噛みしめて理解することで、コミュニケーションもスムーズになります。
逆に、皆さんがインド出張中に風邪気味となり、手持ちの熱さまし等を気軽に頓服すると、症状が激変(悪化)する可能性があるので、是非「まずは血液検査をして安心しよう」文化を忘れずに!
「笑って学ぶ、医療文化の違い」。それは、異文化理解の第一歩です。