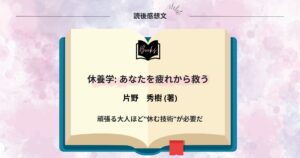「好き」を仕事にしていいんだ——楠木建さんに学ぶ、自分らしい働き方
はじめに:「好き嫌い」がキャリアの出発点?
目次
仕事に「好き嫌い」を持ち込んではいけない——そんな風に思っていた時期が、私にもありました。
でも、楠木建著『すべては「好き嫌い」から始まる』を読んで、その考えがひっくり返されました。

すべては「好き嫌い」から始まる 仕事を自由にする思考法
楠木 建 著
むしろ「好き嫌い」こそが、キャリアの原動力であり、成功の源になる。
そう語る楠木さんの言葉は、これまでの働き方に違和感を抱いていた私には、とても自然に響きました。
戦略とは、好き嫌いの自己表明
「戦略とは、好き嫌いの自己表明である」という言葉が印象的です。
自分が何を好きで、何が嫌いか——その選択をはっきりさせることで、他人と差がつく。戦略は知識や分析だけでなく、自分の感情からも生まれるという視点は新鮮でした。
私たちサラリーマンは、つい「評価されるには?」という視点で動いてしまいがちですが、楠木さんは「自分が好きで続けられるか」に重きを置いています。その積み重ねこそが、長い時間をかけて唯一無二の強みに変わるのだと。
「欲」と「夢」を混同していないか
「将来はグローバルで活躍したい」「経営者になりたい」といった目標。
実は“夢”ではなく“欲”である——この指摘にもドキッとしました。
夢とは、見返りがなくても追いかけたいもの。
欲は「すごい人だと思われたい」「カッコよく見られたい」など他者評価に結びついていることが多い、と。
この区別がつくと、変に焦らず、自分が本当にやりたいことに素直になれるような気がします。
経験は裏切らない、自分だけの納得を大事に
楠木さんが「想像は裏切るが、経験は裏切らない」と語っていたのも共感ポイントです。
ネットや動画で知識や疑似体験は得られても、自分の身体を通した経験は別物。
ビジネス書を読んだだけでできる気になるより、失敗してもしびれるようなリアルな経験の方が、やっぱり血肉になる。そうあらためて感じました。
謙虚な人ができる理由
印象的だったのが、「できる人は謙虚」というくだり。
なぜなら「自分はまだ成功していない」と思っているから、偉そうにする必要がない。これは妙に納得しました。
肩書や役職ではなく、地に足のついた実感のある人ほど、静かに淡々と努力している。
そんな人に、私もなりたいと思いました。
出過ぎた杭は、本当に打たれていいのか
「出過ぎた杭は打たれる」という言葉がありますが、楠木さんの視点は違います。
単に目立つだけで本質的なニーズに応えていない杭は、確かに打たれる。
でも、ニーズに応えられる人間は「代えがきかない存在」になる。
これは組織の中で目立つのを恐れていた自分には、勇気をくれる考えでした。
著者・楠木建さんの人柄に触れて
実は私は、楠木さんの著作やネットの発信から、勝手に「理論派・クールな人」という印象を持っていました。
でも本書を読むと、むしろ内向的で集団行動が苦手、自分の「好き」に忠実な人でした。
そしてシュークリームが好きで、クッキーが嫌い(笑)。
そんなエピソードも含めて、人間味があって、だからこそ説得力のある言葉だったのだと感じました。
おわりに:人生の軸は、自分の「好き嫌い」が教えてくれる
「一生九負」いつも勝てるわけではない。でも、勝てるまでやり続ける人が、最終的に勝つ!
分かっているようで、実行できない……今回改めて実感しています。
本書を通して、自分の好き嫌いに向き合うことの大切さ、自分らしく働くことの価値を再認識しました。
「何が好きか、嫌いか」——その問いに向き合うことで、私たちの人生はもっと自由に、もっと納得のいくものになるのではないでしょうか。