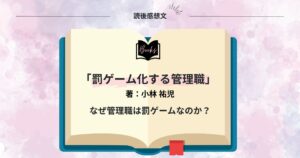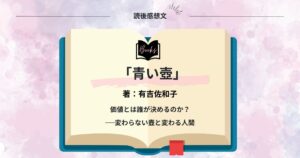権力で理想が変質するとき──『動物農場』は現代を映す鏡
はじめに:トランプと『動物農場』
先日、とある記事で、「トランプ大統領の一連の施策と、それに伴う社会の混乱を見ていると、オーウェルの『動物農場』を思い出す」という一文を目にしました。
まさか、と思いつつ、なぜだか妙に引っかかりました。
『動物農場』といえば、ソ連の政権批判── というのが一般的な読み方です。
私も学生時代に読んだきりで、そういう印象と理解しか持っていませんでした。
けれど、「トランプと動物農場」という意外な組み合わせに触発され、何十年ぶりかに本棚から手に取り、読み直してみることにしました。
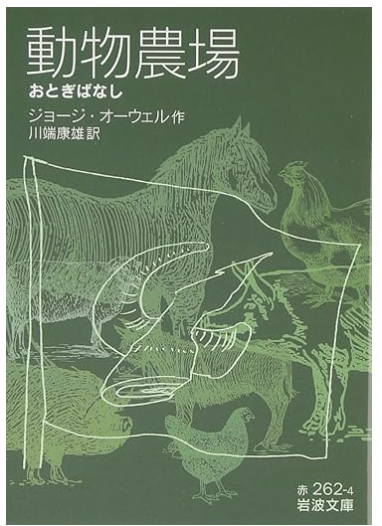
ジョージ・オーウェル 作(1945年)
川端康雄 訳 岩波文庫
久しぶりの再読と視点の変化
正直、昔読んだときには物語の面白さと、動物が人間社会を演じる風刺という“仕掛け”にばかり目がいっていました。
でも、サラリーマン生活を40年以上経験してきた今、まったく違う読後感を味わいました。
読みながら、思わずニヤリとしてしまう。あるいは、「これ、会社と一緒じゃないか」と苦笑する。
かつては寓話だった物語が、いまや現実の職場や社会と重なって見えるのです。
理想と現実のズレ──動物たちの「革命」
物語の発端は、農場の動物たちによる“革命”です。
搾取する人間を追放し、「すべての動物は平等」という理想を掲げて、自らの力で農場を運営していこうとする。
その理念は実に美しいものでした。
「働く者が支配されずに暮らせる世界をつくる」──この純粋な理想に、多くの動物たちが胸を躍らせていました。
しかし、現実はそう甘くありません。
革命のリーダーだった豚たちは、次第に権力を掌握し始めます。当初の理念は都合よく“修正”され、ついには有名な一文が現れます。
「すべての動物は平等である。ただし、一部の動物は他よりももっと平等である。」
これはもはや笑うしかないですね。だけど、どこかで見たような風景です…。
序列と特権の誕生とすり替え
物語では、農場を運営する豚たちがいつの間にか「指導層」になり、他の動物と違う待遇を当然のように受け始めます。
最初は「これは序列ではなく、役割分担だ」と説明されます。実務を担っているから、決断する立場にあるから、というロジックです。
そして最後の場面では「下層動物」という呼び名まで登場します。
この言い回し、どこかで聞いたことはないでしょうか?
「上の立場は責任が重い」「判断が問われるポジションだから待遇に差がある」──これは一見、合理的なようでいて、実は特権の正当化に他なりません。
しかもその特権は、周囲にバレないように、徐々に、そして周到に築かれていきます。
「自分のためではない、組織のためだ」「皆の利益になるから」
そうした言葉で、変化は正当化され、気がつけば理想は骨抜きにされてしまう。
この過程はまさに“人間の性(さが)”そのものだと思いました。
サラリーマン社会との重なり
登場する動物たちには、いろんな「人間の姿」が重なります。
指導層に従順で、文句を言わずに黙々と働く馬のボクサー。
言われたことだけを繰り返す羊たち。
冷めた目で世の中を見ているが、行動は起こさないロバのベンジャミン。
この構図、会社でも見かけませんか?
改革と称して新しいルールが導入されるが、実際は上が得するように設計されている。現場は疲弊しながらも、声をあげない。
「みんなで頑張ろう」と掛け声は響くけれど、その“みんな”に温度差があることには誰も触れない──。
この物語は、ソ連だけでなく、いまの会社組織、日本社会、ひいてはあらゆる集団に当てはまる、普遍的な構造を描いているのだと思います。
終わりに:人間とは何か
『動物農場』の最後、二足歩行を始めた豚と人間が同じテーブルで談笑している様子を見て、他の動物たちは「もはや、どちらが豚でどちらが人間なのか区別がつかなくなった」と語ります。
理想を掲げて始まった改革が、いつの間にか権力の温床となり、かつての敵と同じ姿になる──。
これは、政権の話ではなく、組織、会社、そして人間社会そのものの話です。
そして何より、『動物農場』は「私たちは同じ過ちを繰り返す存在である」という苦い真実を突きつけてきます。
笑って読みながらも、背中がひやりとする。
まさに、それがオーウェルの魅力であり、この物語が時代を超えて読まれ続ける理由なのだと、改めて実感しました。