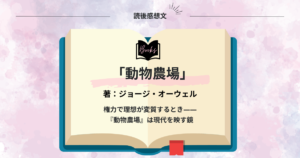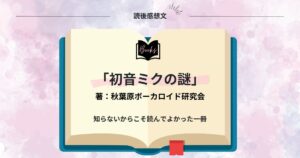「青い壺」が旅する人生──OBOG読書会から始まった時間旅行
出会いはOBOG読書会──「今、話題の50年前の本」
目次
先日、大学のOBOGでの読書会に参加しました。
そこで紹介されたのが、有吉佐和子の『青い壺』という小説です。
「50年前に書かれた短編集なのに、いま文庫のベストセラーになっているんですよ」と言われ、驚いたのが正直なところです。有吉佐和子さんといえば、『複合汚染』『恍惚の人』といった社会問題を描く硬派な作家という印象を持っていました。
けれど、その日の読書会で「これはぜひ読んでみてください、今だからこそ響くものがある」と強く推薦されたこともあり、興味を持って早速手に取りました。

『青い壺』とはどんな物語か?
『青い壺』は、ある陶芸家が焼いた青磁の壺を軸にした13の連作短編から成る作品です。
その壺は、さまざまな人々の手に渡っていきます。退職後の夫婦、嫁姑問題に悩む女性、高校時代の同級生たち、スペインに帰国する修道女など、多様な背景を持つ登場人物が、それぞれの人生の一場面でこの壺と出会うのです。
この構成が本当に見事で、各話は独立していながらも、壺という「静かな観察者」がすべてをつないでいくような、不思議な連続性があります。
青磁の壺が映す、人の業と温もり
印象に残ったのは、どの話にも“人間くささ”が描かれていることです。壺を買ったことで家族間に摩擦が起きたり、過去の後悔を思い出したり、あるいは予想外の救いになったり──壺そのものは何も語らず、何も変わらないのに、持つ人間によってその「意味」は刻々と変化していきます。
ときに壺は誤解され、ぞんざいに扱われもしますが、それでもその存在が、人間の感情や関係性を鮮やかに浮かび上がらせていくのです。
価値とは誰が決めるのか?──変わらない壺と変わる人間
物語のクライマックスでは、壺が美術評論家の手に渡り、その価値が「宋時代の真作では?」と疑われる展開になります。
それまで一度は“粗大ごみ扱い”されることもあった壺が、一転して「名品」とみなされるのです。
この描写はとても象徴的です。
価値とは誰が決めるのか?
時代や環境が違えば、同じモノでも評価がまったく変わる──これは壺に限らず、人間や人生にも通じるテーマだと思いました。
人生は良い時も、そうでない時もあります。
でも、それ自体の“本質”は何も変わっていないのかもしれない。
受け取る側のまなざしが、すべてを決めている──そう思えるのです。
壺が旅したように、本も人をめぐる
面白いことに、読み終えたこの本を、今、私は葉山に住む知人に渡しています。
「良かったら読んでみて」と。
ふと思いました。この壺が巡ったように、本もまた人の手を旅していく。そして、その本を読んだ誰かに、小さな感情の波や人生の問いを残していくかもしれません。
今、その知人がこの本をどう読んでいるのかは分かりません。
でも、もしかしたら、その人の中にもまた、壺のように何かを映し出しているのかもしれない──。そんなふうに想像しています。
縁と人生、そして読後の静かな問い
壺は最終的に、再びその陶芸家の手元に戻ってきます。まるで運命に導かれるように。
これは「縁」というものを象徴しているようで、私は強く心を打たれました。
人と人との縁、物と人との縁、それがどこでどうつながっていくかは分かりません。
でも、巡り巡って戻ってくるものがある──そう思うと、人生もまた捨てたものではない、そんな気がしてきます。
おわりに
『青い壺』は、ただの短編集ではありませんでした。人間の愚かさや優しさ、美しさを、静かに、しかし鮮やかに映し出す「物語の鏡」でした。
この本を読んだことで、私はモノの価値とは何か、人の縁とはどういうものか、そして「今をどう生きるか」について考える機会を得ました。
そして今も、この本は私の手を離れ、別の誰かの人生をそっと照らしているかもしれません。