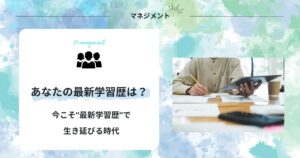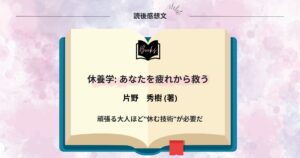「空気バイアス」が日本を動かす?──『「空気」の研究』を再読して見えたこと
勉強会で飛び交った「空気」
ある勉強会で、ある言葉が何度も登場しました。
それは「空気」。
「空気が悪い」「空気が淀んでいる」「空気を読むな!」
さらには、「会議は論理で始まり、最後は空気で決まる」との声まで。
極めつけは、「日本の戦争は空気で始まった」という発言──冗談とも言い切れず、重く残りました。
その場で誰かが言いました。
「これ、空気バイアスって呼ぼうよ!」と。
本棚の奥から『「空気」の研究』を再読
その後ふと思い出し、自宅の本棚にある山本七平の『「空気」の研究』を再読しました。内容はおぼろげでしたが、改めて読むと、現代の私たちの感覚と驚くほどリンクしていたのです。
この本は、日本社会を覆う「空気」という名の同調圧力を精密に分析しています。
論理や事実よりも、「場の雰囲気」や「なんとなくの了解」によって物事が決まる──その構造に鋭く切り込んだ名著です。

「空気」の研究 山本七平 著
空気とは「見えない意思決定システム」
著者が警鐘を鳴らすのは、「空気による支配」がもたらす無責任さ。
誰が決めたかが曖昧になり、「なんとなくそうなった」が意思決定の根拠になってしまう。
そしてその「空気」に逆らう者は異端と見なされ、排除されやすい。
たとえば戦時中、「特攻は当然」とする空気があり、人の命すら空気で決められていたという話を聞き、私は愕然としました。
空気をバイアスで読み解く
この「空気」は、心理学で言うところの『バイアス(認知のゆがみ)』としても説明できます。
中でも、以下の3つが密接に関連しています:
・同調バイアス(Conformity Bias)
周囲に合わせてしまう心理。反対意見が出ないまま意思決定が進行する原因に。
・権威バイアス(Authority Bias)
空気そのものが「見えない権威」となり、逆らいにくくなる。
・集団同調性バイアス(Groupthink)
集団の結束を優先しすぎて、異論を封じ込み、誤った判断をしてしまう。
これらのバイアスが“空気”という名のフィルターを通して強化され、論理的思考を麻痺させていくのです。
今こそ必要な「水を差す勇気」
山本七平は「空気に水を差す人間が必要だ」と語ります。
それは、会議で「ちょっと待って」と言える勇気であり、飲み会での悪ノリを止める一言かもしれません。
空気を読むな、とは言いません。
でも、「空気に流されすぎない」視点は、組織にも社会にも必要です。
本書は40年以上前に書かれましたが、その警鐘は今なお有効です。
日本の会議や政治、学校、SNSまでもが空気に揺れ動く時代。
だからこそ、空気の正体を知ることは、私たちの“知的自衛”になるのだと再認識しました。