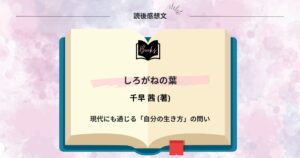インド人の“だめもと要求”に学ぶ交渉力 ― 鍋ひとつから見える文化の深み
はじめに ― インド人はなぜ「要求が多い」と言われるのか
目次
インドの人と接していると、「とにかく要求が多いな」と感じることがあります。
しかもその要求は、「ダメで元々、でも言ってみる」という“だめもと精神”に貫かれています。
一見わがままにも見えるこの姿勢ですが、歴史や文化を知ると実に合理的。
今回は、特定技能生との鍋探しエピソードを交えながら、インドの要求文化をのぞいてみましょう。
歴史と文化から読み解くインド人の「ダメもと力」(谷口私見)
カースト制度への反発
身分や仕事を縛られた社会では、「言わなければ通らない」という実感が強く、自己主張が生き抜く知恵となりました。
たくさんの人口と競争社会
14億人を超える人口の中では、遠慮していては埋もれてしまいます。声を大にして要求を伝えるのはサバイバルの方法でもあります。
宗教と欲望の肯定
ヒンドゥー教は「カーマ=欲望」を人生の目的のひとつとして認めます。欲を語ること自体が自然で、文化的に肯定されているのです。
植民地支配と交渉文化
イギリス統治下で権利を得るには、交渉と主張が不可欠でした。「要求を口にする」ことは生存戦略だったのです。
特定技能生とIHコンロの“鍋事件”
お世話をしている特定技能生が職場を変わるので引っ越しをして、アパートが変わりました。
勤務している会社メンバーに手伝ってもらえる市内引っ越しなので、特に問題ないだろうな・・と思ったら、
「コンロがガスからIHに変わっているので、すべての鍋がつかえません!」との緊急連絡が入りました。
埼玉では有名なスーパー「ヤオコー」に行って、フライパンと深鍋を買いました。
しかし、米を炊くにはこの深さでは足りないとのこと。
「より高くて(深くて)4L以上の容量がほしいです」
「米炊くのに4Lも必要?」
「米を炊くと米汁が噴き出るので、大きな鍋が必要です」
「この鍋がないと、今夜からごはんが食べれません! 是非さがしてください!」
と言われても、4L以上の鍋って一般的でもないし、スーパーでは見つからなかったので、
「アマゾンと楽天でさがしてください。欲しい鍋があれば私に送ってください。私がネット注文して明日会社に届くようにします!」
と言いつつ、今夜のごはんが心配だったので、皆と行きつけ(ってほどでもありませんが、ママさんとは仲良しです)のインド料理屋さんで、チキンビリヤニ(大盛)を2つ買って渡しました。
しかし、夜になっても連絡がありません。
そろそろ情報もらわないと、アマゾンでも明日到着にならないぞ! と思い、自分でアマゾンを検索して、4L以上の深鍋を3つ選んで、「これはどうだろうか? 今連絡もらえれば明日までに会社に届くよ!」と伝えたら即レスありました。
「今の鍋でコメが炊けることがわかりました。よって追加の深鍋はいらないです」
結末と学び ― 「だめもと要求」の力
この経験で学んだのは、インド人にとって「要求を口にすること」は単なる願望の表明ではなく、可能性を広げるための戦略だということです。
日本人は「言って迷惑をかけるくらいなら黙っておこう」と考えがちですが、インド人は「言わなければ絶対に叶わない」と考える。
両者の違いは大きいですが、どちらも生きてきた環境の産物です。
おわりに ― 日常の中にある文化の知恵
IHコンロ用の大鍋ひとつをめぐる攻防でしたが、その背景にはインドの歴史や文化、そして「だめもとでも言う」という知恵がありました。
要求の多さは、単なるわがままではなく、生きるための合理性と交渉力の表れ。
日本人が持つ「遠慮の美徳」と、インド人が持つ「だめもと要求」。どちらも学ぶ価値がある文化です。
日常の小さなエピソードを通じて、異文化理解の奥深さと面白さを改めて感じました。