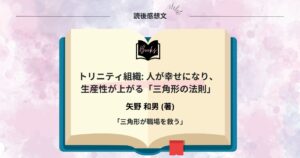インド人が見た「差別」――大阪・道頓堀での一言から考える文化の違い
道頓堀で出会った“ある光景”
大阪・道頓堀を出張中のインド人と歩いていたときのことです。
グリコの看板の前で写真を撮り、食の街らしくインド料理店に向かっていました。
その道中で、アジア系と思われるご夫婦を見かけました。
奥様は電動で自走するスーツケースに乗り、ご主人は荷物を持って早歩きでついていきます。

私は思わず「自走スーツケース、初めて見たけど便利そう」と感心していました。
すると同行していたインド人が突然、「差別だ(Discrimination)」と一言。
私は驚いて「え、どこが差別なの?」と尋ねました。
「差別だ!」というインド人の一言
彼の説明はこうでした。
「奥様が楽をして、ご主人が荷物を持っている。これは差別だ。荷物を持つのは奥様の方だろう!」
その言葉に、私は一瞬理解が追いつきませんでした。
私にとってそれは“夫婦の助け合い”に見えたのですが、彼の文化的背景からは“役割の逆転”に映ったようです。
インド社会に根付く男女の役割観
以下は私の個人的な意見ですが……
インドでは、今でも多くの家庭で「男性=家の外で働く」「女性=家庭を守る」という価値観が根強く残っています。荷物を持つ、身の回りを整えるといった行為は“女性の役割”とされることが多いのです。
もちろん都市部では変化も進んでいますが、無意識のうちにこうした考え方を持つ人は少なくありません。
若者にも残る伝統意識の実例
「そんなのは年配の人だけの話では?」と思うかもしれません。
しかし、私の周囲の若いインド人の中にも、似た価値観が見られました。
以前、日本を訪れたインド人の兄妹(兄27歳、妹21歳)を東京で案内したときのことです。
二人は買い物が好きで、妹は両手いっぱいの袋を持ちながらお土産を選んでいました。私は一時的に袋を持ってあげたのですが、それを見た兄は驚き、「何をしているんだ!」と言って袋を取り上げ、再び妹に持たせました。
同様の場面を、別のインド人甥姪(甥35歳・姪24歳)でも経験しました。
こうした行動は偶然ではなく、男女の役割分担を当然とする意識が、教育や家庭の中で受け継がれていることを示しています。
文化の違いが生む「差別」という感覚
「差別だ」という言葉は、日本人にとっては“相手を見下す行為”を指すことが多いですが、インド人にとっては“「役割から外れた行動」に対する違和感”を指すこともあります。
つまり、同じ言葉でも文化的背景が異なると、感じ方も全く違うのです。
道頓堀でのあの一言は、単なる誤解ではなく、社会的価値観の違いが生んだ“差別観”のズレを映し出していました。
私たちが学べること
グローバル化が進み、多様な人々が共に働き、旅をし、暮らしています。
その中で「差別」という言葉を使うとき、相手の文化や背景を理解しようとする姿勢が欠かせません。
インド人が感じた「差別だ」という違和感も、彼らの社会の鏡にすぎません。
異なる価値観に触れたときこそ、「なぜそう思うのか?」を対話することで、お互いの理解を深められるのではないでしょうか。
※ちなみに動くスーツケースをネットで見つけました!