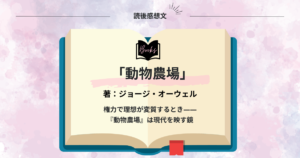なぜ管理職は罰ゲームなのか?『罰ゲーム化する管理職』を読んで考えたこと
日曜朝の勉強会でシステム会社の人事をされているSさんからの推薦本です。
研修企画を作成している際にこの本を読んで、「管理職をサポートしなければ」と強く思ったそうです。
それを聞いて、強い関心を持ちました。
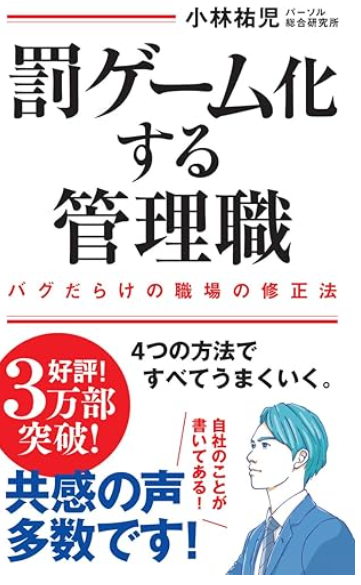
罰ゲーム化する管理職
小林祐児著
インターナショナル新書
はじめに:管理職はなぜ「罰ゲーム化」したのか
目次
かつて出世コースとされた「管理職」。
しかし今、多くの企業でこのポジションは誰もが避けたい“罰ゲーム”と化しています。
日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)が2023年4月に実施した調査によると、一般社員の77.3%が「管理職になりたくない」と回答しています。
この割合は2018年の72.8%から上昇しており、管理職志向の低下が進んでいることが示されています。また、管理職になる前は否定的だったものの、実際に管理職となった後は「続けたい」と感じる人も多いことが分かりました。
管理職は、責任は増す一方で権限は減り、部下の育成、ハラスメント防止、業績管理、メンタルケア、さらには上層部への報告まで、すべてを一手に担う……そんな実態を赤裸々に描いたのがこの本です。
管理職はつらい・・・
本書では、現代の管理職が直面する課題を多角的に分析しています。
管理職が孤立し、疲弊しているのは、単なる本人の資質や努力不足ではなく、構造的な問題です。
たとえば、従来型の「管理職はなんでも知っていて当然」という幻想が根強く残っていること、また支援体制が整っていないことが大きな要因です。
ピラミッドから文鎮型へ:組織構造の変化と限界
組織の階層は年々フラット化しています。
いわゆる「文鎮型組織」では、1人の管理職が抱える部下の数が10人を超えることも珍しくありません。
しかし、米軍の分隊(Squad)が10人で構成されているように、人が実際に“直接マネジメントできる限界人数”は10人程度が目安とされています。これを超えると、心理的にも物理的にもマネジメントは破綻します。
日本型キャリアの歪みと孤立する管理職
日本企業では、新卒一括採用で幹部候補生として入社し、30代で選別が始まります。そして40歳を過ぎると、同期でありながら明確な「職位格差」が生まれます。管理職に昇進した者は、「勝者」として見なされる一方で、誰にも助けを求められず、孤独に陥ることも多いです。サポート体制は不十分で、むしろ「できて当然」という無言の圧力があります。
管理職に必要なのは「引っ張る力」ではなく「支える力」
今日の現場は複雑で変化が速いです。「すべてを知っているリーダー」ではなく、「必要な支援をつなぐコーディネーター型リーダー」が求められています。管理職はチームを引っ張るのではなく、後方から支える存在に転換すべき時期に来ています。
1on1神話と現場のギャップ
多くの企業が「1on1ミーティング」を導入していますが、現実にはうまく機能していません。
理由のひとつは、今の管理職自身が「質の高い1on1」を上司から受けた経験がほとんどないことです。そのため、何をどうすれば良いか分からず、形式的な対話に終始してしまいます。
管理職を支援するために必要なこと
会社は「1on1をやれ」と命じるだけでなく、管理職が安心して実践できるような支援が必要です。たとえば、拘束時間を減らす、マネジメントに集中できる時間と環境を整備する、ピアサポート制度を導入するなど、構造的な支援が不可欠です。
おわりに:今こそマネジメントの再定義を
「管理職=万能型プレイヤー」という幻想を捨て、支援型・共創型マネジメントへと舵を切ること。
これが、管理職が罰ゲームではなく「やりがい」と「誇り」を取り戻す第一歩となります。

〉を乗りこなす-300x158.jpg)