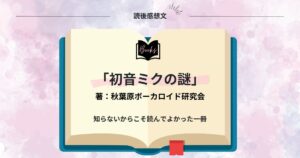「忘れられた人々」が動かす時代へ――『カウンターエリート』を読んで考えた日本の未来
はじめに──トランプ政権から「カウンターエリート」へ
目次
「カウンターエリート」という言葉を初めて知ったのは、アメリカのトランプ政権に関する記事を読んだときでした。トランプ氏が大統領に選ばれたとき、過激な発言、政治経験のないビジネスマンとしての出自、SNSでの発信――どれも既存の政治家像とは大きく異なっていました。
だが、読み進めるうちに、トランプ政権を支えた「忘れられた人々」の存在、そしてそれを代弁する“カウンターエリート”という存在が、この時代に不可欠な現象であることを感じました。そしてその理解を深めたいと思い、手に取ったのがこの『カウンターエリート』という書籍です。

カウンターエリート (文春新書 1492)
石田 健 著
知的エリートへの反発と地方の逆襲
トランプ政権の副大統領であるマイク・ペンス氏は、まさにこの構造を象徴している人物です。ペンス氏は、アイビーリーグといった超エリート校出身の知的エリートに対して明確な距離をとっています。ワシントンDCやニューヨークといった大都市圏のリベラルで高学歴な人々に対して、保守的で宗教心の篤い中西部の価値観を代弁してきました。
この対立構造は、「都会 vs 地方」「高学歴 vs 実務派」「理想主義 vs 常識」といった対比に集約されています。
カウンターエリートとは、従来の知的エリートとは異なる立場から社会に影響を与える人々のことであり、既存の秩序や価値観に異議を唱え、民衆の声を代弁する存在です。
SNS時代のリーダー像と「アメリカ・ファースト」
特に印象深かったのは、トランプ大統領が一貫して「アメリカ・ファースト(自国優先)」を掲げ、その主張をSNS、特にTwitter(現X)で直接発信していたことです。公式な記者会見ではなく、キャップをかぶり、支持者に語りかけるスタイルは、それまでの政治家像を一新しました。
この姿勢こそが、従来のエリート層に対するアンチテーゼであり、民衆との距離感を縮める最大の要因でした。情報の非対称性を破壊し、「わかりやすさ」と「感情」に訴えかけるトランプの発信力は、支持層にとって極めて魅力的だったのです。
日本におけるカウンターエリートの可能性
では、日本にも同様の「カウンターエリート」は現れるのでしょうか?
現在の日本の政治においても、東京を中心とした知識層や財界、官僚機構への不信感は根強くあります。また地方では、人口減少や医療・交通インフラの衰退などの課題が積み重なり、「都会の論理では解決できない」という声が強まっています。
しかし、日本では依然として「高学歴=優秀」という価値観が強く、政治の世界でも東大・京大出身の議員や官僚が幅を利かせています。
カウンターエリートが登場するには、民衆の側が「自分たちの代弁者を信じて、動かす」という民主主義の力を取り戻す必要があります。その点で、日本にはまだ時間がかかるかもしれませんが、確実に「変化への種」はまかれつつあると感じています。
たとえば、地方発のベンチャー企業や、NPO、地域政党など、既存の枠組みの外から「暮らしの視点」で声を上げる人々が少しずつ増えています。彼らが広範な共感を得て、全国規模の政治ムーブメントに成長する可能性は、十分にあるでしょう。
おわりに──エリートと民衆の間にあるもの
『カウンターエリート』を通じて、私は「エリート」と「アンチ・エリート」の単純な対立ではなく、「声なき人々の声をどうすくい取るか」という視点の重要性を再認識しました。情報化社会の中で、表面的な言葉や数字では語れない現場の実感が、どれほど重いか。だからこそ、SNSのような「直接つながるツール」が政治を変えていくのでしょう。
日本が本当に変わるとすれば、それはカウンターエリートのような“異質な存在”が現れたときかもしれません。その時、私たちは「既存の知性」だけに頼るのではなく、「民意の直感」にも耳を傾けられるかどうかが問われます。
『カウンターエリート』は、そんな時代の問いを突きつける一冊でした。