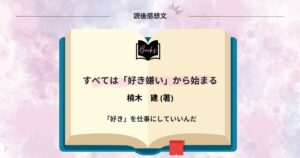『休養学:あなたを疲れから救う』──頑張る大人ほど“休む技術”が必要だ
なぜ今、「休むこと」を学ぶ必要があるのか
目次
「ちゃんと休んでる?」と聞かれて、「週末は寝てるし、テレビも見てる」と答える人は多いかもしれません。でも、朝起きても疲れが取れない、連休明けに余計しんどい──そんな経験はありませんか?
私は、夕食後にとても眠くなり、30分ほどウトウトしています。
これは、最近よく言われている「睡眠負債」を抱えているのだと思います。
ですから、きちんと6時間以上寝ていますが、実は「休み方」が適切ではないのでは? と感じたことがこの本を読んだ一番のきっかけです。

休養学:あなたを疲れから救う
片野 秀樹 著
それは、“休んだつもり”になっているだけかもしれません。
「つもり」が曲者です。わかりにくい存在ですね。
そんな中、 今、注目されているのが「休養学(Restorative Science)」という考え方です。ただの「休息」ではなく、心身を回復させるための戦略的な休み方を学ぶ学問。頑張り続ける現代人にこそ必要な、“休む技術”です。
間違った休み方があなたを疲れさせている
たとえば、スマホを片手にベッドでYouTubeを見続ける──これは「娯楽」かもしれませんが、脳は情報処理でフル稼働しており、まったく“休んで”いません。
また、仕事を忘れようと無理に遊んでも、「ちゃんとやれてない罪悪感」が心を締めつける。
こうした「休んだのに、疲れが取れない」という悪循環は、間違った休み方の典型です。
休むことは、スキルであり、戦略です。
感情・脳・身体のそれぞれに合った「回復のための行動」をとることで、初めて“本当の休養”が得られるのです。
科学でわかる“本当に回復する”休養法
休養学の観点から、効果的な休み方はいくつかあります。
◯ アクティブレスト(積極的休養)
軽い散歩やストレッチなど。身体を適度に動かすことで血流を促し、脳疲労も軽減。
◯ マインドフルネス
呼吸に意識を向け、今ここに集中することで、心のざわつきが整う。
◯ 質の高い睡眠
睡眠時間よりも「入眠直後の90分の深い眠り」が重要とされる。睡眠環境や習慣の見直しが回復力を高める。
◯ 情報遮断タイム
SNSやニュース、メールなどから一定時間距離をとる「デジタルデトックス」も、脳の休養には効果的。
これらは「一見、ささいなこと」ですが、積み重ねることで大きな違いを生みます。
休養バイアスを疑おう──「休む=サボり」ではない
「休むなんて、甘えじゃないか」
「もっと頑張ってる人もいる」
こう思ってしまう人もいるでしょう。しかしこれは、いわば“休養バイアス”です。
特に昭和世代の働き方は、「根性で乗り越えろ」が美徳とされてきました。けれど今は、AI、リモートワーク、マルチタスク社会──働き方も疲れ方も、質が違うのです。
現代は、意図的に休まなければ壊れる時代。
「休む=サボる」ではなく、「休めない=危ない」という視点への転換が必要です。
仕事も人生も、休養次第で変わる
私は最近、意識的に「自分のエネルギー残量」を見るようにしています。「あと何%で動けなくなるか?」を把握する習慣です。そして、その残量が50%を切る前に、回復タイムを入れるようにしています。
感覚的なものですが、無理してもどこかで反動が来ます。反動を避けるためにも、「エネルギー残量」を少し意識するだけで世の中が変わる(ような感じが)します。
この習慣を始めてから、仕事の質も、人間関係も、安定するようになりました。
疲れてからでは遅い。倒れてからでは遅い。
休養は予防です。自己管理の柱です。そして、あなたを救う技術です。
頑張っているあなただからこそ、どうか「休む」ことを、ちゃんと学んでみてください。