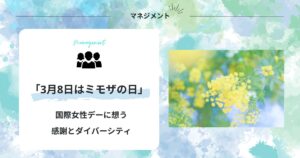DEIの現在地:政治は揺らいでも、職場は前を向く
はじめに
DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)は、ここ数年で企業活動や社会的責任の一環として広く浸透してきた考え方です。
しかし、アメリカにおいてトランプ大統領がこの流れに批判的な発言を繰り返したことにより、DEIの方向性に大きな変化が起きています。
今後DEIはどうなるのか——最近の新聞、雑誌、ネット検索などの情報をまとめて、私なりに考えをまとめました。
アメリカにおけるDEIの転換点
2020年、BLM(Black Lives Matter)運動を背景に、多くの企業や団体がDEIの方針を強化しました。
しかし、トランプ大統領は「DEIはアメリカに悪影響を及ぼしている」と批判し、イーロン・マスク氏も「DEIはDIEだ」と痛烈なコメントを発して「DEI逆行」が始まりました。
しかしこれは、米国がかなり程度ジェンダー平等を推進してきた、という事実があり、その前提があっての動きです。
対して日本では、まだ多様性に関する制度整備や文化的理解が進みきっていないため、日本における「DEI逆行」という表現そのものが適切ではありません。
現場でのDEIはどうなるか
政治的にはDEIの逆行・後退が進む可能性があるものの、企業の現場ではDEIの重要性は引き続き認識されています。
米国のアップルやコストコのように、反DEIの株主提案を否決する企業も存在します。
これは、ダイバーシティ推進が単なる理念ではなく、実際に事業の継続や競争力維持に関わる経営課題であるという理解が進んでいるからです。
また、株式市場もこの動きを冷静に見ています。
反DEIの政治的な発言にもかかわらず、DEI推進企業の株価に大きな影響は見られていません。これは、市場がDEIの実利的な価値を理解していることの現れでしょう。
日本社会におけるDEIの意味
日本では少子高齢化が進み、人手不足が深刻化しています。
このような社会背景の中で、多様な人材を受け入れ、活かすDEIの考え方は企業活動にとって不可欠です。性別・国籍・年齢・障がいの有無を問わず、働きやすい環境を整えることが、組織の存続や成長に直結します。
「日本でもDEIは行き過ぎている」という論調も時折見られますが、これは誤解と言えるでしょう。
日本におけるDEIはまだ始まったばかりであり、これから制度として、文化として根付かせていく必要があります。
日本企業の経営陣にはいまだに「Old Boys Network(オールドボーイズ・ネットワーク:主に男性同士の旧知の人脈を通じて築かれる、排他的かつ非公式な支援や機会の提供ネットワークのこと)」を肯定するグループが存在します。そのグループからすればDEIは「厄介な存在」なので、それを排除したいと思うグループが存在することは事実です。
企業とDEI:未来への視点
企業にとってDEIは、リスク回避やCSRだけでなく、人材確保、イノベーション、ブランド価値の向上にもつながる戦略的課題です。
経営層がその意義を理解し、持続可能な形で取り組むことが今後ますます重要になります。
政治的な風向きが変わったとしても、現場の課題は変わりません。
現場で求められるのは、現実に即した対応です。
日本の企業も、世界の潮流とともに、独自のDEIのあり方を築いていくことが求められます。
おわりに
政治的にDEIが後退する動きがある中でも、企業現場ではその重要性が揺らいでいるわけではありません。むしろ、人材不足や社会的な要請に応じて、実践的・戦略的な取り組みがさらに求められています。
DEIは一過性の流行ではなく、社会と企業の持続可能性を支える根幹的な価値観です。
今こそ、現場の声と社会のニーズをつなぎ、より現実的で効果的なDEIの推進が必要とされているのです。
ただ、気を付けなければならない点を挙げます。
DEIの推進は「世の中の流れだから」ではありません。DEIを推進することが、「多様な視点から業務成果が高まるから」です。慢性的な人手不足の日本企業において「多様な人材活用のため」等の目的を示し、目標と期限を明確にしつつ推進することが大切です。